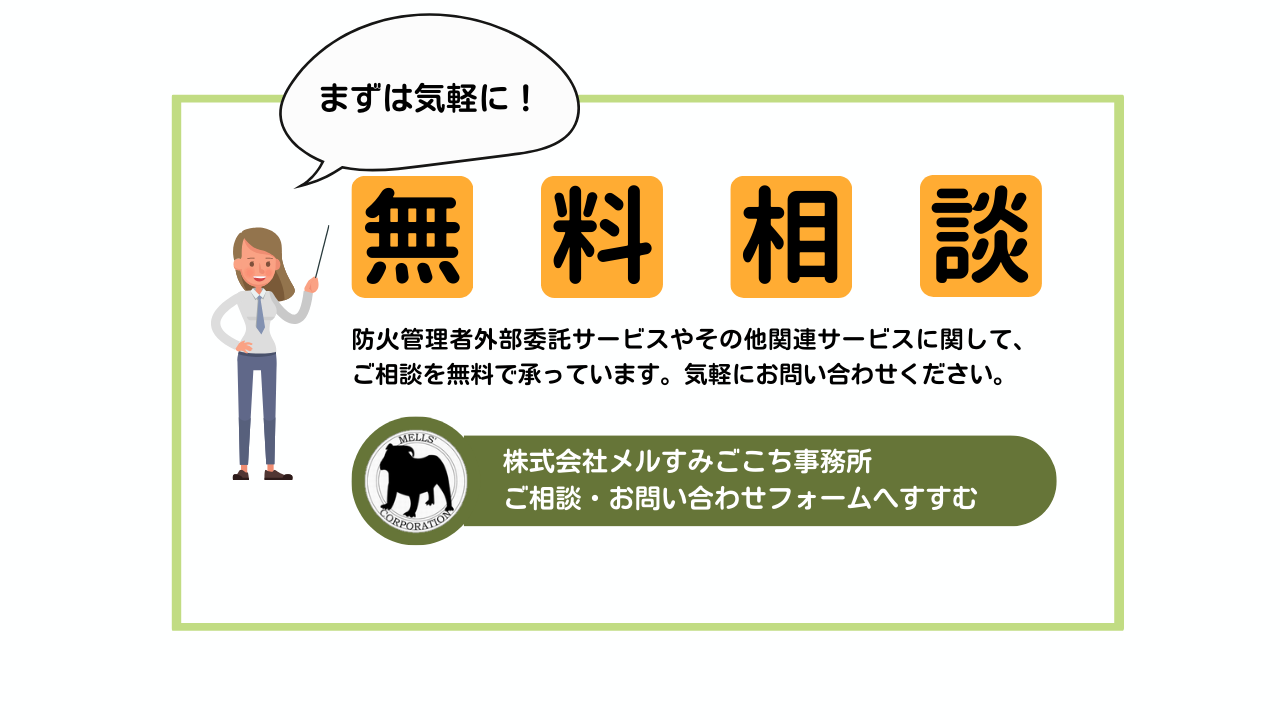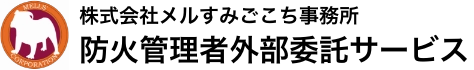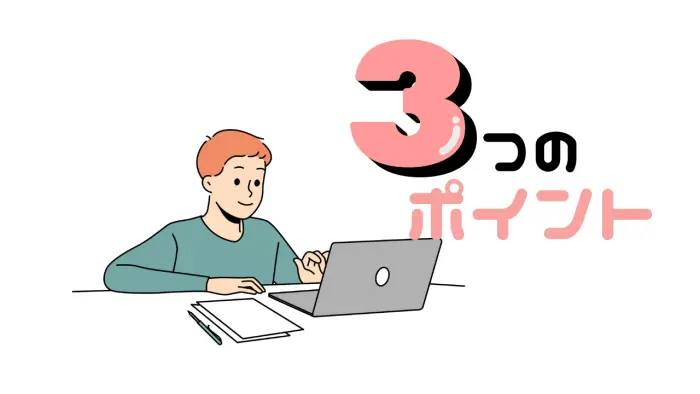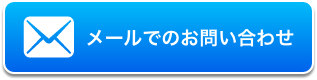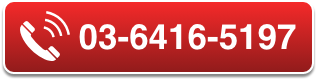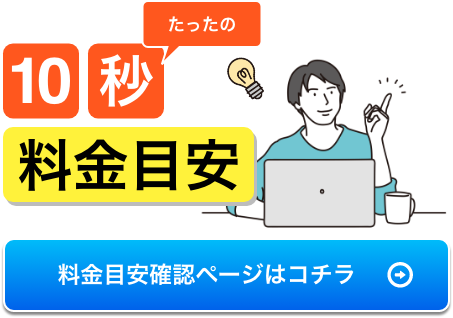近年、企業に求められる姿勢として「コンプライアンス遵守」がますます重要になっています。特に、消費者の安全や信頼に直結する分野においては、一つの不祥事が大きな社会問題となり、企業の存続やブランド価値に深刻な影響を与えることがあります。私たちが提供している防火・防災関連の業務においても、それは決して例外ではありません。
本コラムでは、実際に起きた「某コンビニチェーンの消費期限偽装事件」を例に挙げながら、当社がどのようにコンプライアンスを重視し、日々の点検業務の質を維持・向上させるために取り組んでいるのかをご紹介します。
防火管理者外部委託サービスに求められるコンプライアンスと品質管理の重要性
今般報道されている某コンビニチェーンの消費期限表示の不適切運用では、店内調理されたおにぎりや弁当のラベルが貼り替えられ、消費期限が延長されていたことが明らかになりました。なお、この問題は外部からの告発や行政調査ではなく、社内調査によって判明したものです。
食品偽装があったこと自体はファンのひとりとして残念ではありますが、社内調査によって不正を把握し、品質を担保する仕組みが機能していた点には学ぶべき点があります。大手企業であれば当然の体制ともいえますが、こうした取り組みの重要性が改めて示された事例であり、私たち自身も不正を未然に防ぎ、早期に発見できる仕組みづくりの必要性を再確認するきっかけとなりました。
当社は、【防火管理者外部委託サービス】を全国規模で展開しています。このサービスは消防法に基づく防火管理者の責務に則り、建物の安全を維持し、多くの人々の命や財産を火災から守るという、極めて大きな使命を担っています。そのため、コンプライアンス違反が生じることのないよう、常に防止と徹底に力を注いでいます。
本サービスでは、防火管理者業務の一環として、原則毎月お客様の物件を訪問し、防火管理に特化した点検を実施しています。消防設備の状態確認や避難経路の安全確保など、日常では見落とされがちなポイントをチェックし、改善が必要な場合には速やかに対応するとともに、管理権原者へ報告する仕組みを整えています。
おかげさまで事業は拡大を続けており、それに伴い現場で点検を担うスタッフも増加し、現在では全国で90名を超える規模となりました。これは当社にとって大きな強みである一方で、運営上の新たな課題も生み出しています。
特に重要なのは、「点検の質をいかに均一に保つか」という点です。点検スタッフは全国をカバーできるようエリアごとに配置されているため、お客様が特定のスタッフを指名することはできません。そのため、どの地域でも同じ水準のサービスを受けられることが大前提であり、地域差や担当者による品質のばらつきをなくすことが求められます。
そこで当社では、点検業務の質を安定的に維持・向上させるため、専任の監督スタッフによる「抜き打ち点検」を導入しています。これは単なる監視や取り締まりを目的としたものではなく、現場での点検が当社の基準に沿って確実に行われているかを検証し、必要に応じて改善指導や教育につなげるための重要なプロセスです。
抜き打ち点検は全国規模で実施されており、スタッフ全員が常に一定の緊張感を持ちながら業務に臨める体制を整えています。こうした仕組みによって、当社はお客様に対して「どのエリアでも、誰が担当しても変わらない品質」をお約束できるよう努めています。

抜き打ち点検でスタッフの意識と点検精度が高まる理由
抜き打ち点検は、通常の定期点検や報告チェックとは異なり、事前に対象スタッフへ知らせることなく実施されます。具体的な流れは次のとおりです。
1.対象の選定
ランダムに、あるいは特定の懸念がある現場を選びます。
2.現場確認
専任スタッフが現地を訪問し、点検が規定どおりに行われているか、記録と実態が一致しているかを確認します。
3.評価とフィードバック
問題が見つかれば是正指導を行い、必要に応じて後日、追加教育やマニュアルの改訂につなげます。
このサイクルを継続することで、点検スタッフの意識は自然と引き締まり、日常の点検においても「誰に見られても恥ずかしくない業務を行う」という緊張感が維持されます。その結果、業務の精度は一段と高まり、点検内容の確実性や報告の信頼性も向上します。抜き打ち点検は単なる監査ではなく、スタッフのモチベーションを保ち、組織全体の品質を底上げする効果を持っています。
さらに、実際に抜き打ち点検を行うと、当初は想定していなかった改善点が浮かび上がることも少なくありません。普段の点検では気づきにくい「思い込み」や「慣れ」が見直されることで、現場ならではの課題が明確になるのです。小さな見落としが大きなリスクにつながり得ることを現場で再認識できる点も、抜き打ち点検の大きな価値といえます。
たとえば、ある現場では子供用の自転車が置かれており、担当者は「十分な避難経路が確保されている」として不備にあたらないと判断していました。確かに、現時点で火災が発生しても避難に支障はないかもしれません。しかし、防火管理者が想定すべきは「夜間に大地震が発生し、その後火災が起きる」という最悪のケースです。停電により誘導灯が消えて真っ暗になった場合、自転車が倒れて避難経路を塞ぐ可能性や、体の不自由な方が避難しなければならない状況など、現実的に起こり得るリスクを考慮する必要があります。
一方で、防火点検の際に廊下の私物に警告文を貼り、移動を促したところ、わずか数日後の抜き打ち点検で改善が確認されたケースもあります。当社の警告文は、お客様の資産に傷をつけないよう養生テープを使用し、塗装等への影響を避ける工夫をしていますが、その一方で視覚的なインパクトが強いため、撤去につながる可能性が非常に高いのです。
コンビニ事件から学ぶ、仕組みと文化の両立の重要性
大切なのは、抜き打ち点検という「仕組み」そのものだけでなく、それを支える「文化」を根付かせることです。
- コンプライアンスを損なう行為は決して容認されないという価値観を全社員で共有する
- 不備を見逃さず、迅速かつ的確に改善へ結びつける
- 常にチェックされることを前提とした業務習慣を自然に身につける
こうした文化があってこそ、形式的なコンプライアンス遵守にとどまらず、実質的な安全と信頼の確保につながります。
先般のコンビニチェーンにおける消費期限偽装問題は、私たちに「不適切な行為を未然に防ぐ仕組み」と「早期に問題を発見できる体制」の両方が欠かせないことを改めて認識させる出来事となりました。
この教訓を踏まえ、当社でも日々の点検業務が適切に実施されているかを確認するため、専任スタッフによる抜き打ち点検を継続的に行っています。そこで得られた気づきは、スタッフ教育やマニュアルの改善に反映し、業務品質のさらなる向上へとつなげています。そして、こうした取り組みを常にブラッシュアップしながら継続していくことの大切さを、改めて学ぶ機会となりました。
今後もコンプライアンスを最優先に据え、社会からの信頼に応えられるよう取り組みを続けてまいります。