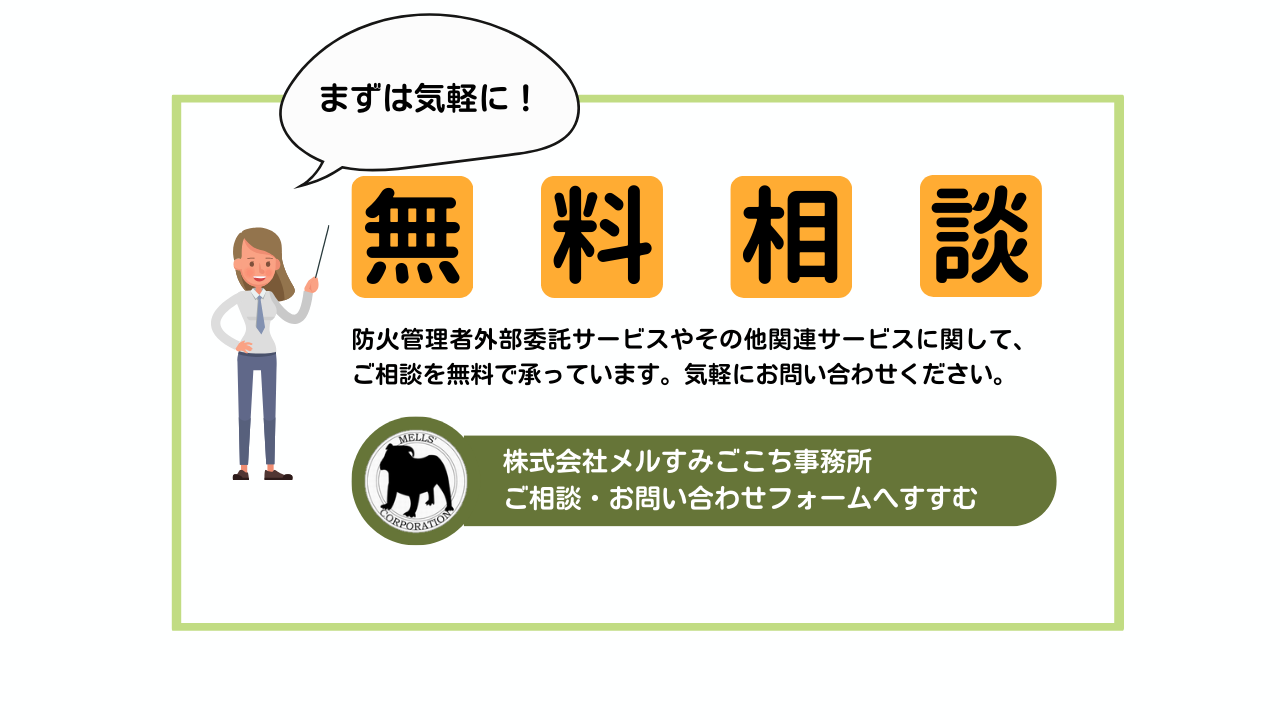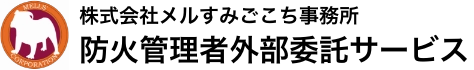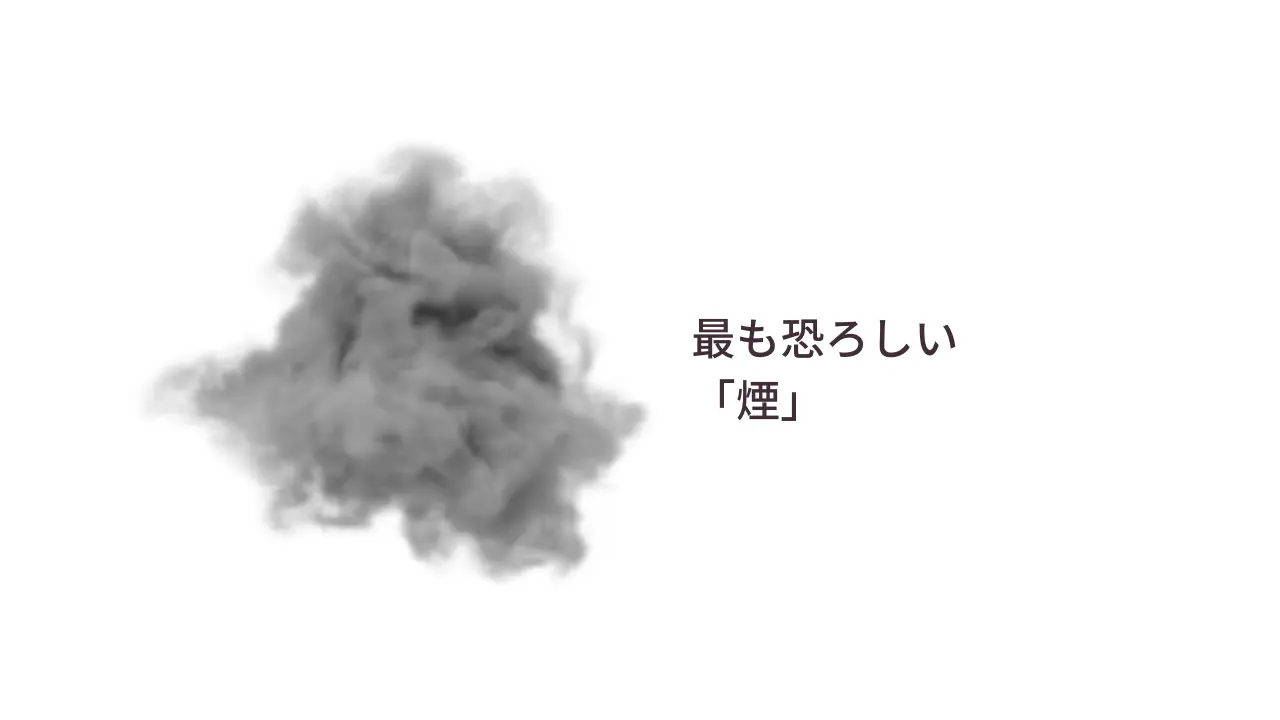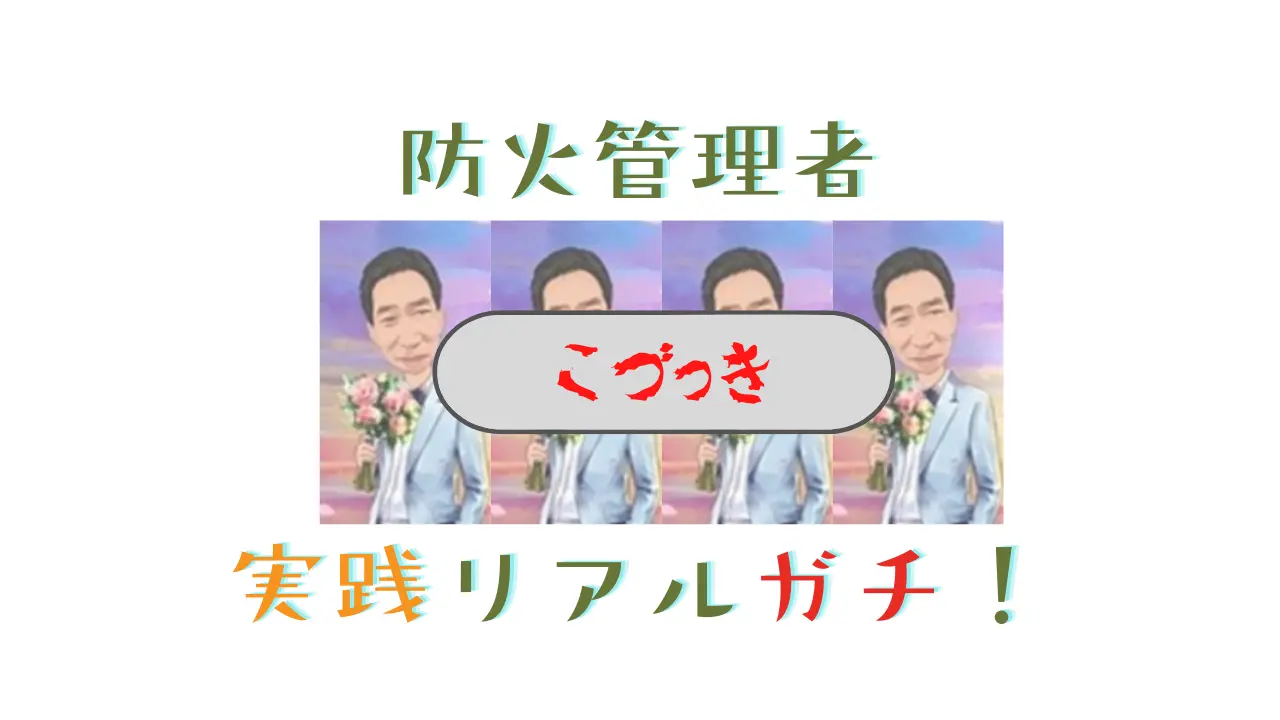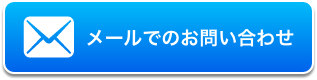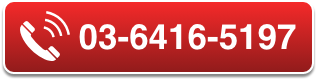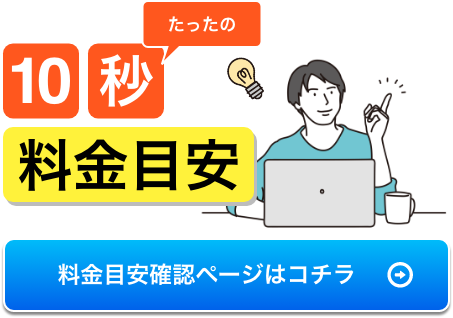これが実際の防火管理!防火管理者業務①~④を具体的に解説
当社が提供する「防火管理者外部委託サービス」では、防火管理者として実施すべき業務内容を、お客様との間で締結する「防火管理者等業務に関する契約書」に明記しております。当社が防火管理者として選任されることで、法令に定められる防火管理者としての責務を確実に遂行することをお約束します。
とはいえ、防火管理者に求められる業務の具体的な内容について、詳細まで把握されているお客様は決して多くないのが実情です。そのため、本サービスをご利用いただくうえでのご理解を深めていただけるよう、東京消防庁のホームページに記載されている防火管理者の職責をもとに、当社がどのように各項目に対応しているのかを、全編・後編の2回に分けて説明します。
東京消防庁のホームページには防火管理者が実施すべき業務について、以下の8項目が明記されています。
《防火管理者の責務》(消防法施行令第3条の2一部抜粋)
- 「防火管理に係る消防計画」の作成・届出
- 消火、通報及び避難の訓練を実施
- 消防用設備等の点検・整備
- 火気の使用又は取扱いに関する監督
- 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理
- 収容人員の管理
- その他防火管理上必要な業務
- 必要に応じて管理権原者に指示を求め、誠実に職務を遂行する
《出典》東京消防庁:「管理権原者」とは・「防火管理者」とは
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/office_adv/jissen/p03.html
これら、防火管理者に求められる各責務について、当社がどのように対応しているのかを、以下に具体的に説明します。
1.「防火管理に係る消防計画」の作成・届出
消防計画とは、建物や施設において火災等の災害に備え、火災予防・初期消火・避難誘導などの体制や手順を定めた、非常に重要な計画書です。日常的な防火管理業務はこの消防計画に基づいて行われるため、防火管理者の選任が必要な建物では、必ず備えておくべき基本書類です。
防火管理者には、この消防計画を作成し、管轄の消防署に届け出る義務があります。各自治体のホームページなどで作成例を確認することができるため、未経験の方でも対応は可能です。ただし、自治体ごとに書式が異なるうえ、複数ページにわたる詳細な記載が求められることもあり、「難しい」「手間がかかる」といった声も多く寄せられています。
当社では、現在1800件を超える物件で防火管理者業務を受託しており、その豊富な実績をもとに、全国すべての自治体に対応した消防計画の作成が可能です。自衛消防組織に関する記載を含め、消防計画の作成から消防署への届出までを一貫して対応します。管理権原者や建物の利用者の皆様に安心していただけるよう、建物の用途や規模に応じた、適切かつ実効性の高い計画を作成します。
2.消火、通報及び避難の訓練を実施
防火管理者講習では、消防訓練の実施方法について基礎的な知識を学ぶことができますが、実際に訓練を行う際には、事前の案内や必要書類の準備、訓練当日の運営、さらには報告書の作成など、さまざまな実務的負担が伴います。加えて、訓練の実施頻度は建物の用途や規模に応じて法令で定められており、年1〜2回の実施が義務付けられています。なお、「声をかけても参加者がいない」という理由で訓練を行わないことは認められておらず、参加状況にかかわらず、法令に基づいた適切な訓練の実施が求められます。
当社では、消防署への届出、訓練告知、当日の訓練運営、実施報告書の作成までをすべて代行し、不参加者向けには注意喚起の手引書を配布するなど、法令に基づく訓練を確実に実施します。これにより、お客様の負担を最小限に抑えながら、適切な訓練体制を維持することが可能です。

3.消防用設備等の点検・整備
ここで求められている点検・整備は、半年に1回実施される消防設備士等の有資格者による法定点検とは一線を画します。法定点検では、専用の検査機器を使用し、消防設備の状態を詳細に確認したうえで、建物の用途に応じて定められた期間内に消防署へ報告書を提出する義務があります。しかし、防火管理者に求められているのは、こうした専門的かつ制度的な点検ではありません。
とはいえ、年2回の法定点検だけでは、消防設備の状態を常に良好に保つには不十分なケースがあるのも事実です。日常的な点検の積み重ねこそが、防火管理の実効性を高める重要な要素となります。
当社では、原則として毎月実施している「巡回防火点検」の中で、消火器、屋内消火栓、誘導灯などの消防設備について、目視を基本とした確認を行っています。たとえば消火器であれば、標識の掲示状況、外観の損傷や錆の有無、圧力ゲージの状態などを確認し、異常があれば速やかに管理権原者(建物の所有者等)に報告・対応を依頼します。
また、当社では、より精度の高い点検を実現するため、専門業者が実施した消防設備点検報告書の共有をお願いしています。法定点検の内容を把握することで、当社による巡回防火点検と相互に補完・連携を図ることが可能となるためです。なお、報告書には防火管理者の氏名を記載する欄が設けられており、内容を確認のうえ、当社にて記載を行うことも可能です。

4.火気の使用または取扱いに関する監督
この項目も、現地確認を伴う業務であり、防火管理者が実際に建物を訪れなければ対応できません。火を扱うテナントの有無にかかわらず、巡回防火点検の際には、火災の原因となりうるリスクがないかを確認し、問題があれば対象テナントへ注意喚起や警告等を行います。
たとえば、喫煙が禁止されている共用部に吸い殻が落ちていたり、段ボールなどの可燃物が避難経路となる廊下や階段に放置されていた場合など、危険性の高い状況には即時対応を行います。処分可能と判断されるものについては、状況記録の撮影後、当社で責任をもって撤去します。
なお、放火や不審火による火災は現在も多く発生しており、統計によると、近年では出火原因の上位に「放火」や「放火の疑い」が挙げられ、これらを合わせた件数は「たばこ」を上回っています。特に放火は共用部で発生するケースがほとんどで、火災を未然に防ぐためには、「放火されやすい環境をつくらないこと」が非常に重要です。
当社では、こうした火災リスクの低減にも積極的に取り組んでおり、共用部の巡回点検や状況に応じた改善提案などを通じて、放火の防止に努めています。なお、この統計や具体的な対策については、当社のコラム「放火を防ぐために、今日からできる4つの方法」で詳しくご紹介していますので、ぜひご参照ください。
後編に続きます。