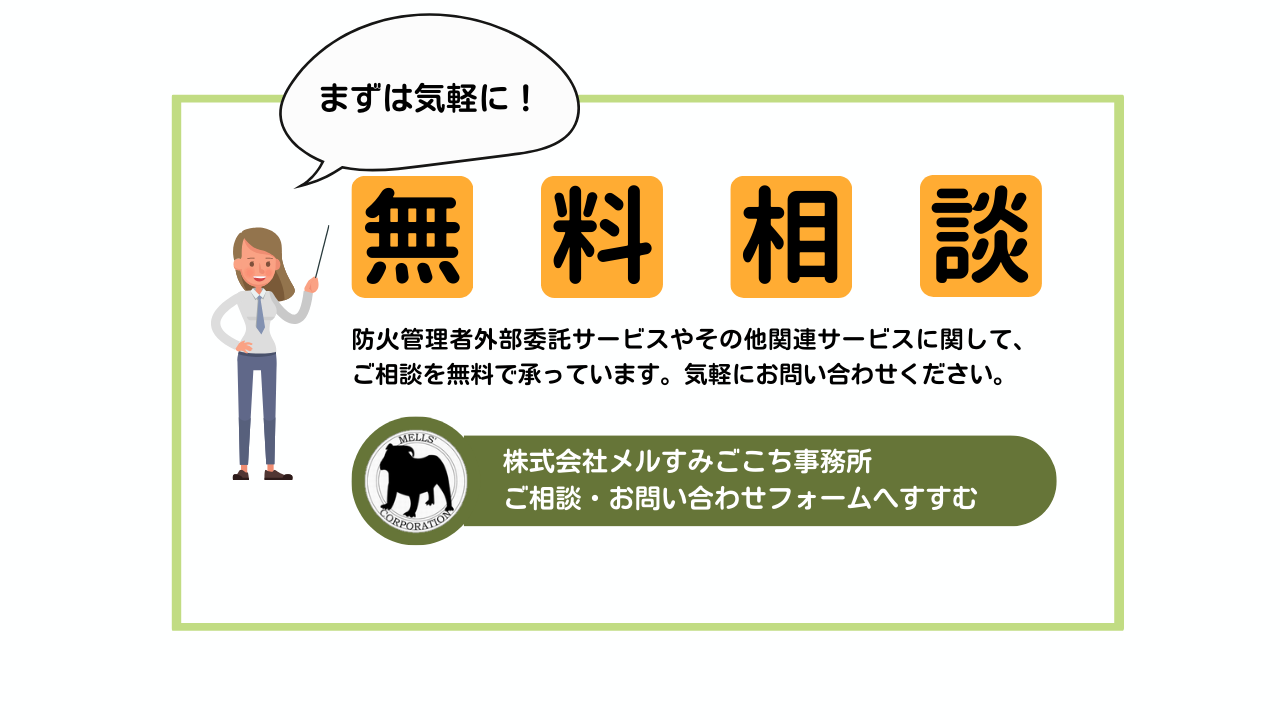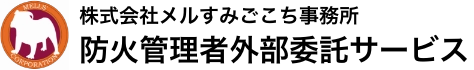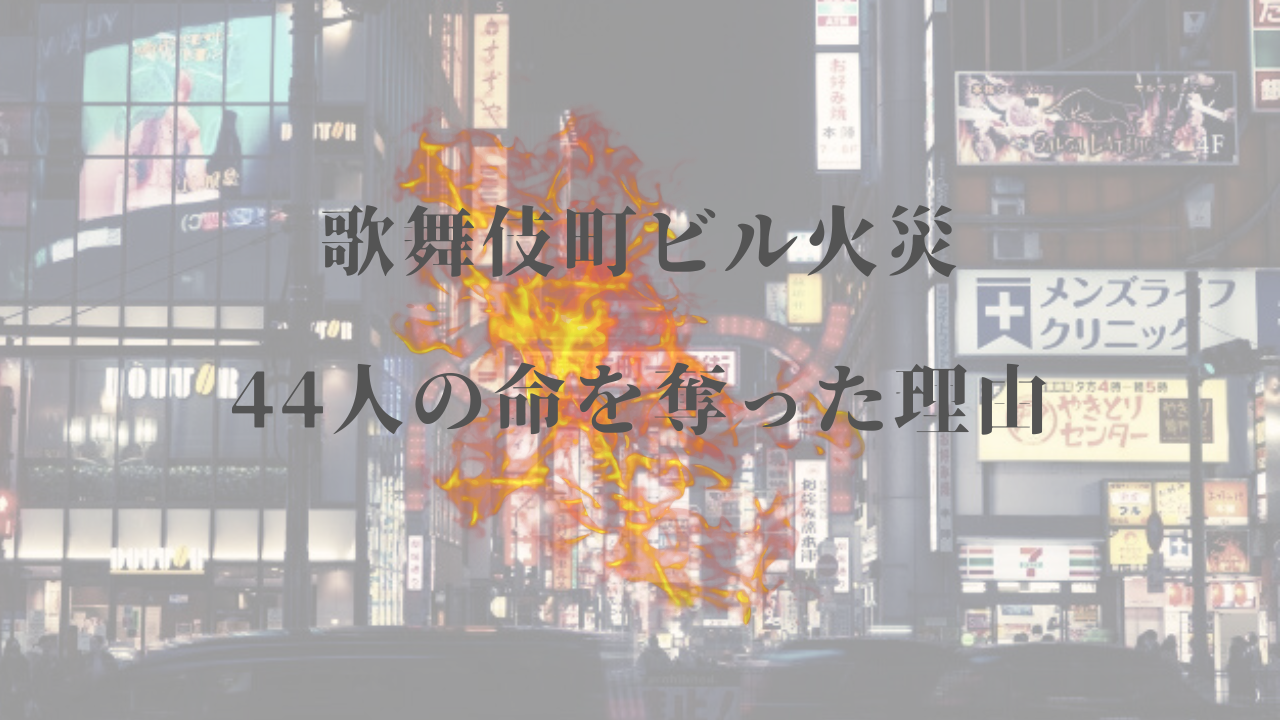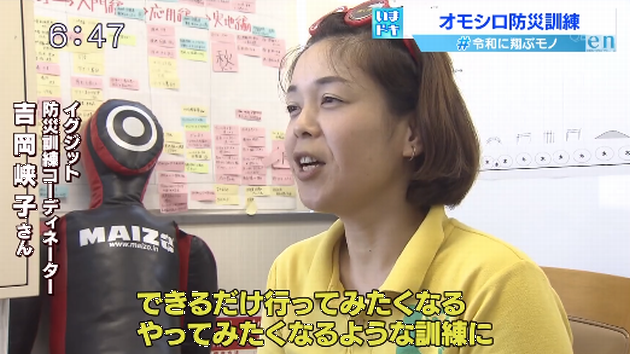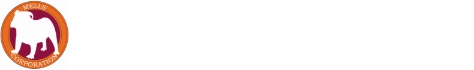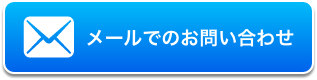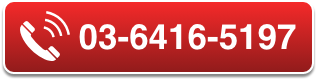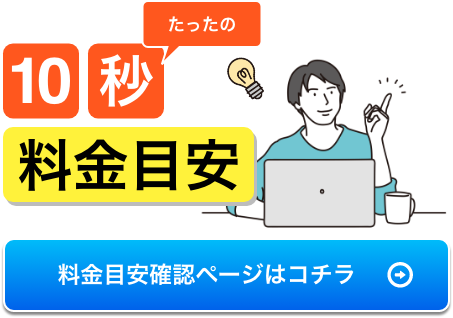歌舞伎町ビル火災:44人の命を奪った悲劇
44人もの尊い命が奪われた歌舞伎町ビル火災。この事件は、消防法が大きく改正されるきっかけとなりました。20年以上前、新宿の小さな雑居ビルで発生したこの火災が、なぜこれほどまでに被害を拡大させたのか。当時の状況を振り返ってみましょう。
事件概要
- 2001年9月1日 東京都新宿区歌舞伎町の雑居ビルで起きた火災
- 44人が死亡し、3人が負傷
- 出火原因は放火とみられているが、2022年8月現在も未確定
- 多くの死者を出した原因は、避難通路の確保が不十分であったため
- ビルオーナーやテナント関係者に執行猶予付きの有罪判決が下り、消防法の改正につながる
ずさんな防火管理
- ひとつしかない避難階段にゴミ袋や衣装ケース、ビールケースなど、ほぼ隙間なく置かれていた
- ゴミや私物が障害となり、階段に設置された「防火戸」が機能しなかった
- 自動火災報知設備は誤作動が多いため電源を切られていた
- 防火管理者の選任および消防計画作成が徹底されていなかった
44人の死因はすべて急性の一酸化炭素中毒によるものでした。一酸化炭素中毒とは、火災時に発生する煙に含まれる一酸化炭素を吸い込むことで、血液中の酸素が極端に不足し、極めて緊急性の高い危険な状態になる中毒です。
この非常に危険な「火災時の煙」が、出火地点である3階のエレベーター前から瞬く間に建物全体に広がった原因は、共用部である階段や踊り場にゴミや私物が散乱していたため「防火戸が正常に機能しなかった」ことにあります。
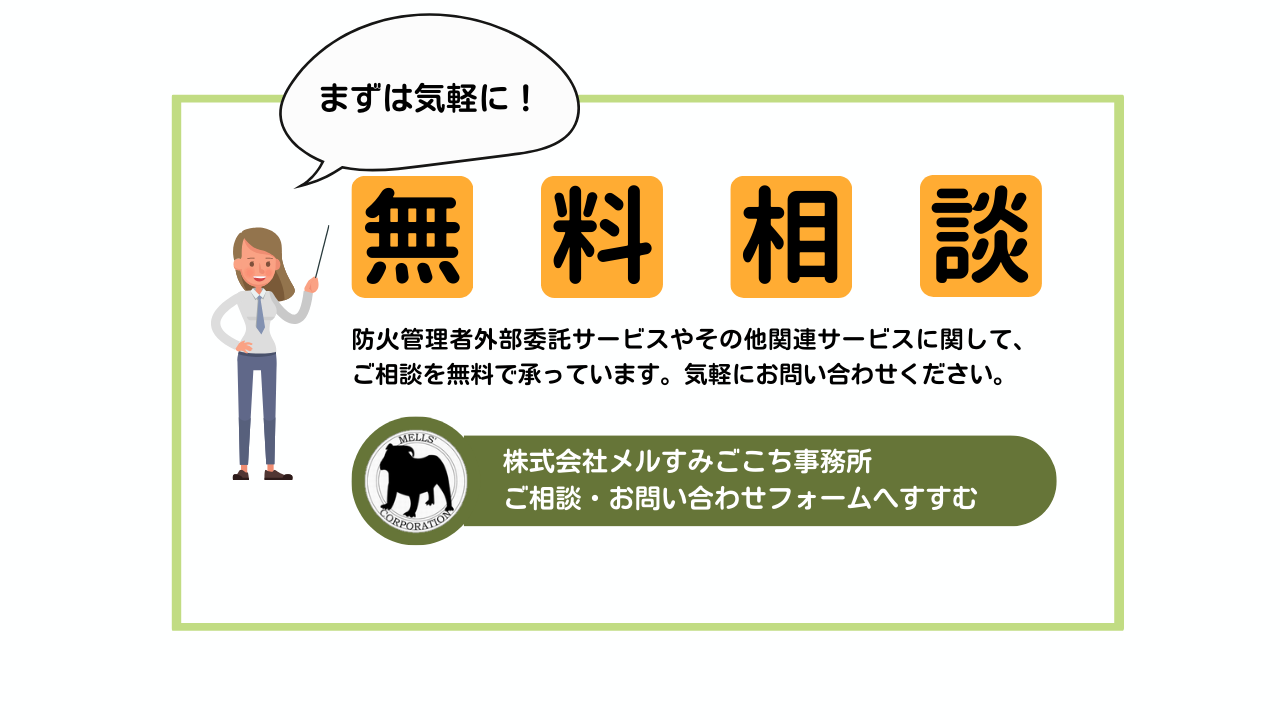
防火戸(防火扉・防火シャッター)の役割と種類
防火戸は、防火扉や防火シャッターとも呼ばれる消防設備で、通常は人が通行できるようになっていますが、火災時には炎や煙の広がりを防ぐように設計されています。防火戸は、火災の際に他のエリアへの延焼を防ぎ、避難路を確保するための極めて重要な役割を果たします。
防火戸には、「常時閉鎖型防火戸」と「随時閉鎖型防火戸」の2種類があります。
「常時閉鎖型防火戸」は、通常は常に閉じられており、人が意図的に開けない限り閉鎖状態を保つ扉です。このタイプの扉は、完全に開放しても自動的に閉まるように設計されており、比較的安価であるため、共同住宅や雑居ビルの内階段などで多く使用されています。
「随時閉鎖型防火戸」は、火災を感知すると自動的に閉鎖される扉で、鉄扉がスイングして閉じられるタイプや、上部からシャッターが降りて閉鎖されるタイプが一般的です。
防火戸は、火災時に「閉鎖」されていることが極めて重要です。この機能が果たされないと、炎や煙が他のフロアに広がり、被害が拡大してしまいます。
煙が広がるスピードは、垂直方向で毎秒約3~5メートル、水平方向では毎秒約0.5~1メートルといわれています。特に、階段などの垂直方向では、人が逃げる速度よりも煙の上昇スピードの方が速く、逃げ遅れると完全に巻き込まれる危険があります。内階段が1つしかない、いわゆる雑居ビルのような不特定多数の人が出入りする建物では、『防火戸が機能しない=避難路が断たれる』ことを意味するため、特に注意が必要です。

日常点検の重要性:防火戸が命を守る瞬間に備えて
巡回防火点検を行う際、換気を目的に防火戸をストッパーで開けたままにしているケースが見受けられます。コロナ対策の必要性は理解できますが、防火管理の観点から見ると重大な問題です。防火管理がどれほど徹底されていても、放火のリスクは常に存在します。
例えば、「京都アニメーション放火殺人事件(※1)」や「北新地ビル火災(※2)」のような事件では、ガソリンなどの揮発性が高い可燃物を使用した放火が行われました。こうした場合、火災が発生した際にストッパーを外して防火戸を閉める余裕はほとんどなく、炎や煙が瞬く間に建物全体へ広がってしまいます。その結果、多くの命が危険にさらされることになります。
さらに、共同住宅(マンション)の玄関ドアも同様に、防火設備としての「防火戸」として設計されています。これにより、ストッパーがなく、常に開放しておくことができない構造になっています。これは、建築基準法に基づく防火規定に従っているためであり、安全性を確保するために必要な措置です。住人が「風通しを良くするために常にドアを開けておきたい」と管理会社に要望を出したとしても、その要求が受け入れられないのは、この防火設備としての重要な役割を果たすためです。
このように、防火戸は火災時に人命を守るために設置されている非常に重要な設備です。コロナ対策で換気を優先したい気持ちは理解できますが、安全を犠牲にすることなく、適切な換気方法を考えることが求められます。放火などの非常時には、防火戸が正常に機能することで、火災による被害を最小限に抑えることができます。そのため、日常的に防火戸が閉じられている状態を保つことが、建物全体の安全性を確保するために不可欠です。
(※1)京都アニメーション放火殺人事件(京アニ事件)
2019年7月18日に京都府京都市で発生した放火殺人事件。アニメ制作会社「京都アニメーション」の第1スタジオに男が侵入し、1階にバケツからガソリンを撒いて放火したことで、スタジオは全焼、社員36人が死亡、33人が重軽傷と、未曽有の大惨事となった。
(※2)北新地ビル火災
2021年12月17日に大阪府大阪市の通称「北新地」にある雑居ビルの4階クリニックで発生した放火事件。クリニックに通院していたと思われる男が、持参した2つの紙袋を蹴り倒し、流れ出た液体にライターのようなもので点火したことで、被疑者を含む27人が死亡、1人が負傷した。