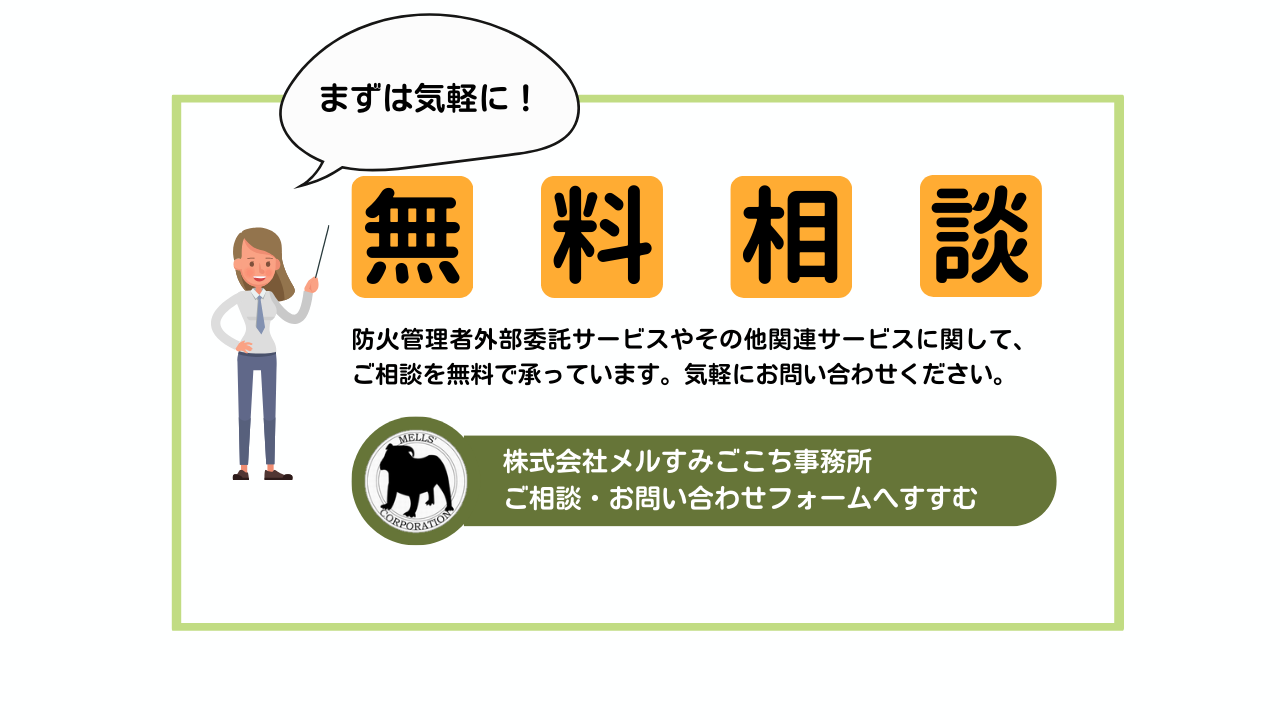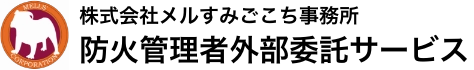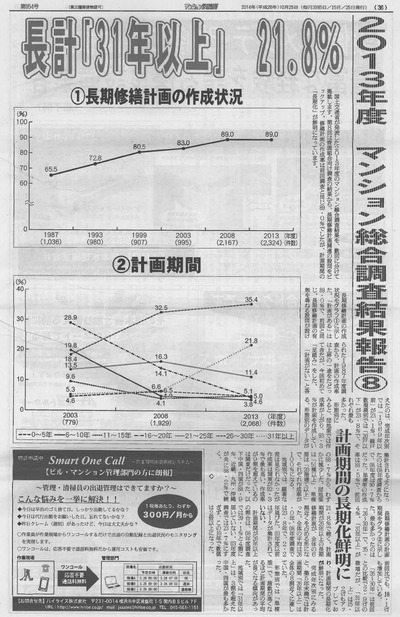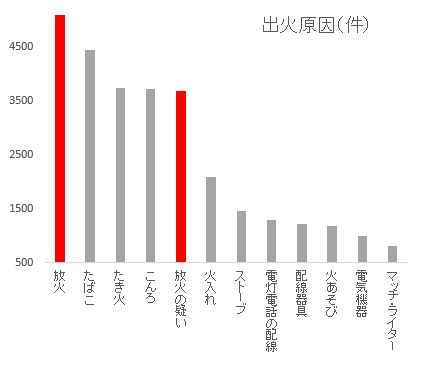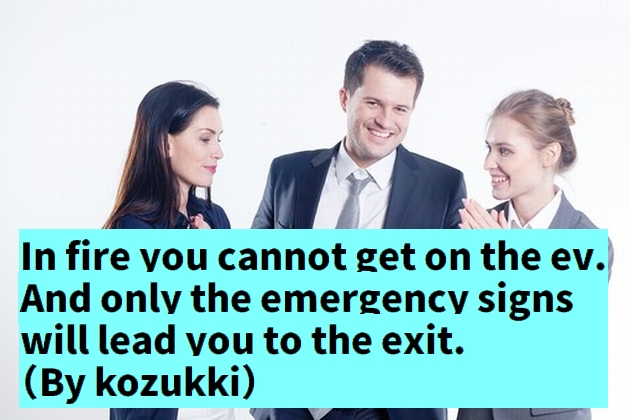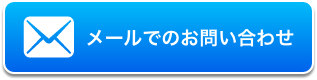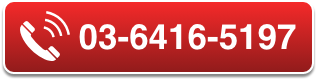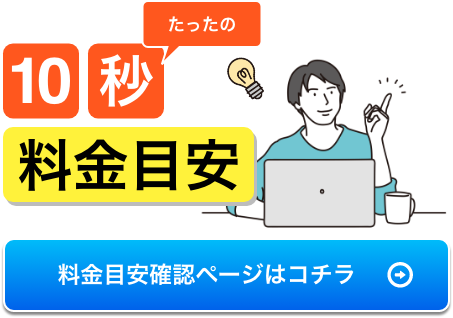香港タワーマンション火災から考える―日本のタワマンは本当に安全か?鍵を握るのは“防火管理”の質―
2025年11月、香港で高層マンションの大規模火災が発生しました。建物は修繕工事中で、外周はすべて足場と防護ネットで覆われており、火災はその足場を伝って上層階へ一気に広がったとされています。死傷者・行方不明者は100名を優に超え甚大な被害となりました。現場では住民の避難が難航しただけでなく、火勢が急速に上層階へ拡大したことで消火活動も極めて困難な状況だったと報じられています。
今回の火災は、日本でも広く報道され、「日本のタワマンでも同じような火災が起きるのでは?」と不安に感じた方も多いのではないでしょうか。しかし結論から言えば、日本のタワーマンションでは“同じ形での延焼”は起こりにくく、構造面・制度面の安全性は世界の中でも突出しています。ただし、誤解してはいけないのは、建物そのものが安全でも、防火管理が機能していなければ火災時の被害は十分拡大し得るということです。
今回の香港火災を「海外の遠いニュース」とせず、日本のタワマンに住む私たちにとっての教訓として整理します。
香港のタワマン火災はなぜここまで拡大したのか
報道されている主な要因を整理すると、以下のようになります。
① 竹製足場と可燃性の防護ネットが“延焼の導線”になった
香港では伝統的に竹で足場を組む文化があり、軽量で扱いやすい一方で可燃性が高いという弱点があります。今回の火災でも、竹足場に加え、使用されていた防護ネットが基準を満たしておらず可燃性だった疑いがあると報じられており、これらが火の通り道となって炎が外壁を縦に駆け上がったとみられています。
日本では大規模修繕時の足場は鉄製であり、養生シートも不燃性のものを使用するため、このような外側からの急激な延焼は起こりにくい構造です。
② 放水が中層階までしか届かず、上層階の消火が困難
はしご車からの放水は、国や地域を問わず実用的には30m前後(10数階相当)が限界です。香港でも同様で、火元が高層側へ急激に広がった結果、外部からの放水が届かず、上層階の消火は建物内から突入するしかありませんでした。高層建築が密集する香港では、近年特に問題視されてきた課題でもあります。
③ 火災報知設備が作動しなかった可能性
現地報道では、警報ベルが作動しなかった可能性のほか、窓部分に外側から発泡スチロール材が使用されていた疑いも指摘されています。事実関係の詳細は現在も調査中ではあるものの、初期警報の遅れと可燃物の存在が避難行動を困難にし、その結果、多くの死傷者を招いた可能性が高いです。
日本のタワマンで“同じ火災”が起こりにくい理由(ハード面)
日本のタワーマンションは、世界の中でも防火性能が非常に高く、“燃え広がりにくい構造”が法律で求められています。こうした仕組みがどのように火災拡大を防ぎ、避難の安全性を確保しているのかについて、以下で具体的に解説します。
①足場・シート・外壁が不燃性で構成されている
日本では、大規模修繕時に設置される足場は鉄製が一般的で、可燃性の竹足場を用いることはほとんどありません。また、足場を覆う防護ネットについても、原則として不燃性または難燃性の資材が使用されるよう基準が整えられています。特にタワマンの大規模修繕では防火性能を重視した資材が選ばれるため、外側から火が一気に駆け上がるリスクは相対的に低いといえます。
②感知器とスプリンクラーによる早期対応
11階以上の住戸にはスプリンクラー設備が原則として義務化されており、煙や熱を感知した早期段階で自動放水が開始されます。また各住戸には煙感知器や熱感知器が設置された自動火災報知設備が備わっており、初期の段階で警報が発報されるため、避難開始が遅れにくい構造になっています。
③防火区画により延焼が“面”ではなく“部屋単位”で抑制される
建築基準法では、一定の面積ごとに防火区画で分けることが求められており、そのために防火戸や防火シャッター、防火壁などが設けられています。あわせて、住戸単位でも防火構造が採用されているため、専有部で発生した火災が隣の住戸へ延焼しにくい設計になっています。こうした区画化の考え方により、住戸が広い場合であっても、ワンフロア全体が一気に燃え広がるような構造にはなっていません
④二方向避難の確保と複数の避難経路
高層マンションでは、建築基準法により共用部として2か所以上の直通階段を設け、フロア全体として二方向以上の避難経路を確保することが義務付けられています。こうした共用部の構造的な要件により、火災時に一つの経路が使えなくなっても、別の方向から避難できるよう設計されています。
また、専有部についても、玄関側だけでなくバルコニー側へ逃げられる構造を採用しているタワーマンションが多く、住戸ごとに複数の避難ルートを確保できるケースが一般的です。そのため、避難経路が一つしかなく、火災時に逃げ場が失われるといった状況は基本的に想定されていません。
日本の高層マンションに求められる防火・避難対策については、東京消防庁が住民向けに分かりやすくまとめた「高層マンションにお住まいの方へ」というガイドがあります。防炎物品の使用や避難設備の基本など、日常の安全に直結する内容が整理されており、本稿の内容を補足する参考資料として一読の価値があります。
《出典》東京消防庁 高層マンションにお住いの方へhttps://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/office_adv/bouen/p06.html

本当に重要なのは“ソフト面の防火管理”
どれだけ建物の構造がしっかりしていても、日常の運用が適切でなければ安全は簡単に損なわれます。実際、香港の火災でも警報設備が作動しなかった可能性が報じられています。これは日本でも同じで、建物自体が強固であっても、防火管理が機能していないタワーマンションでは火災時に大きな危険が生じます。まさにここからが、日本のタワマンで最も重要となる「ソフト面の防火管理」の話です。
日本の強みは「防火管理者制度」
消防法では、一定規模以上のマンションに防火管理者を選任することが義務付けられており、防火管理者は日常的に防火管理上の不備を見逃さないよう点検し、必要に応じて状況の改善や管理権原者(建物オーナーなど)への連絡・報告を行う責務があります。具体的な点検内容は、多岐にわたります。たとえば、
- 廊下や階段などの避難経路に私物が置かれていないか
- 防火戸の周囲に物が置かれ、火災時の閉鎖や延焼防止の機能を妨げる恐れがないか
- 消火器などの消防設備の周囲に私物がなく、緊急時に支障なく使用できる状態か
- 誘導灯の球切れや消火器の異常など、消防設備に不具合や劣化が生じていないか
といった点を確認します。
防火管理者は「選任すれば終わり」ではなく、日常的な点検を通じて適切な管理を継続することが極めて重要です。こうした地道な日常管理の徹底こそが、火災発生時の被害を最小限に抑えるための最も大きな要素となります。
共用廊下に私物があると“延焼より先に”人が逃げ遅れる
火災で最も恐ろしいのは、炎そのものではなく煙だと言われています。煙が共用廊下や階段に回り込み、視界が奪われた状態になると、そこに私物が置かれているだけで大きな障害となり得ます。車いすを利用している方など身体の不自由な方の避難を妨げるだけでなく、健常な人でもつまずいてけがをする危険が高まります。
さらに、共用部に私物が残置される状況は、「自分も少しくらいなら」と周囲の同調を誘発し、放置物が増えていく傾向があります。とくに廊下に自転車が置かれるケースなどは、一つの行為が連鎖反応のように広がりやすく、結果として避難経路の確保が難しくなるため、十分な注意が必要です。
消防訓練・避難訓練が“生死を分ける”
防火管理者には、法令で定められた回数以上の消防訓練を実施する責務があり、この取り組みは非常に重要です。初期消火の方法や正確な119番通報の手順、適切な避難行動を事前に理解しているかどうかで、火災時の避難の成否や生存率は大きく左右されます。
火災のように予期しない緊急事態に直面すると、普段は冷静な人でもパニックに陥り、通報先の119番すら思い出せなくなることがあります。さらに、初期消火の成功率を高めるには、住民が協力して複数の消火器を使用することが効果的ですが、そのためには一人ひとりが消火器の使い方を正しく理解している必要があります。わずかな判断の遅れや操作の誤りが、初期消火の成功を大きく左右してしまうのです。
消防訓練は、こうした緊急事態をあらかじめ疑似体験し、火災を想定した行動を頭の中で整理する機会になります。訓練を通じて危険を具体的にイメージできるようになることで、日頃からの心構えや避難に向けた準備といった重要な行動につながることが期待されます。
まとめ:安全なタワマンを守るのは「建物」ではなく「人」
日本のタワーマンションは、構造や設備の面で非常に高い防火性能を備えており、今回の香港火災のように外側から炎が一気に駆け上がるような事態は起こりにくい設計になっています。しかし、最終的に住民の安全を守るのは建物そのものではなく、日々の防火管理がどれだけ適切に行われているかという点に尽きます。どれほど堅牢なタワマンであっても、防火管理が形骸化すれば、火災時の被害は一気に大きくなり得ます。
香港の火災を日本に置き換えて考えたとき、改めて肝に銘じるべきなのは「構造の強さだけでは命を守れない」という厳しい現実であり、最終的に安全を左右するのは日々の管理の質だという点です。
多くのタワーマンションには防災センターが設置され、警備員や管理員が常駐していますが、彼らが防火管理者に求められる業務をすべて担っているとは限りません。そもそも、防災センターの常駐体制と、防火管理者の選任・実務遂行はまったく別の法的義務であり、この二つは本来切り離して考える必要があります。そのため、防火管理者が不在のままになっていたり、住民に名義だけの選任を依頼して実務がほとんど行われていないといったケースも起こり得ます。
だからこそ、防火管理者が実務を確実に行い、点検・巡回・訓練といった日常の防火管理を途切れさせないことが極めて重要になります。管理組合として防火管理の質を維持するためには、内部の負担や専門性の不足を補う方法として、防火管理者の外部委託サービスを活用するという選択肢があります。
専門の防火管理者が継続的な巡回や訓練、書類作成、消防署対応などを一括して担うことで、タワーマンションが本来備えている高い防火性能を、確かな“実際の安全”へとつなげることが可能になります。
タワーマンションの安全を本当の意味で支えるのは、ハードとソフトの両輪が揃ってこそです。建物そのものの性能に加えて、防火管理の質を着実に確保することこそが、火災から住民の命を守る最も確実な方法だと言えるでしょう。