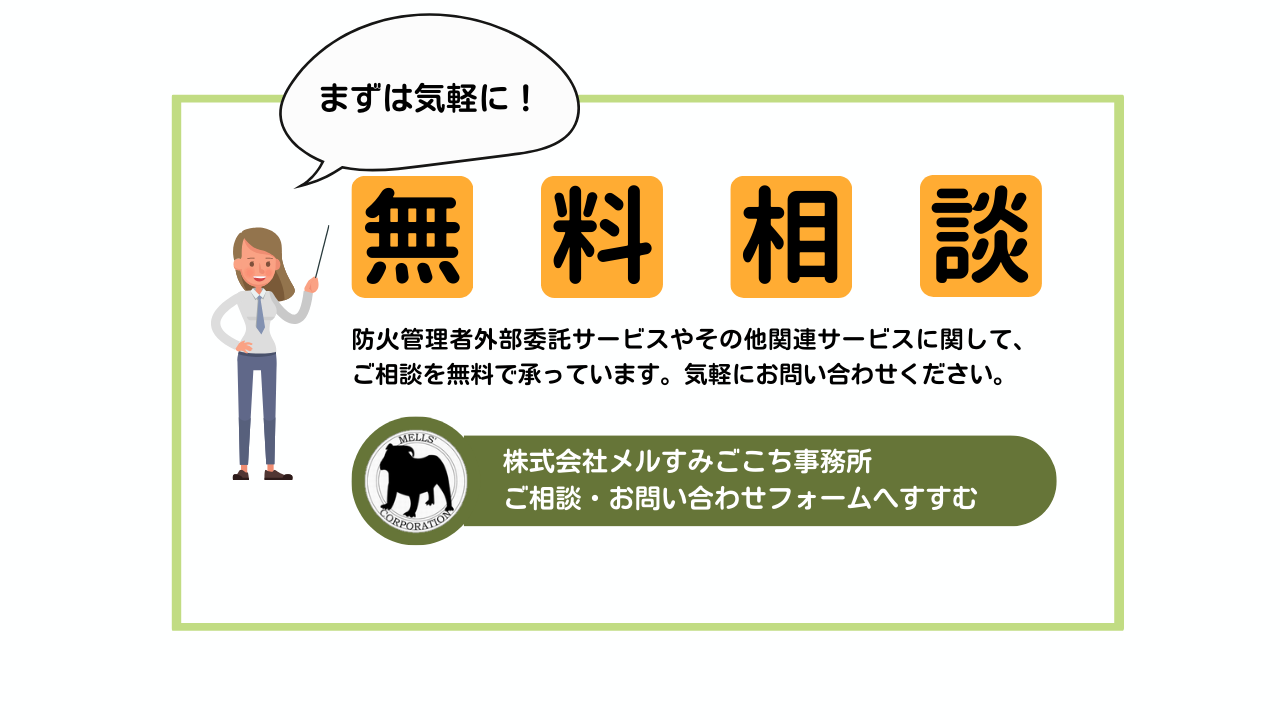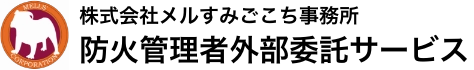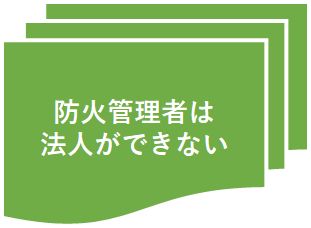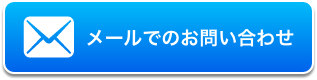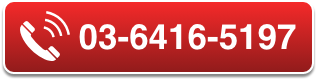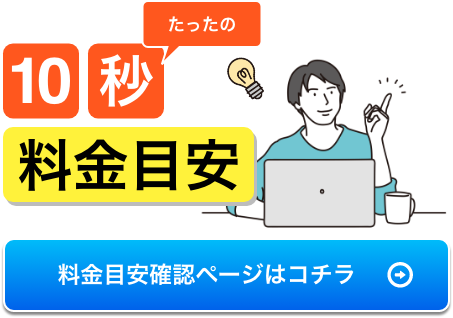防火管理に関するコラムを重ねるたびに、最終的には「歌舞伎町ビル火災」という未曽有の大惨事に行き着いてしまうことに、改めて気づかされます。
今回のコラムでは、総務省消防庁が公表している「小規模雑居ビルの防火安全対策に関する答申」をもとに、なぜあのような悲劇が起きてしまったのか、そして尊い命を守るために、どのような法改正が行われたのかを振り返ってみたいと思います。
《出典》総務省消防庁 「小規模雑居ビルの防火安全対策に関する答申(消防審議会)」(PDF)
https://www.fdma.go.jp/singi_kento/singi/items/tousin_05.pdf
なぜ44人が亡くなったのか?答申にみる歌舞伎町ビル火災の教訓
平成13年(2001年)9月1日未明、東京都新宿区歌舞伎町の中心部にある「明星56ビル」で発生した火災は、5階建て・延べ床面積516㎡という比較的小規模な雑居ビルで起きたにもかかわらず、44名もの尊い命が奪われるという、日本の消防史上に残る大惨事となりました。
この悲劇は、建物の規模や構造が小さいからといって安全とは限らないという厳しい現実を突きつけました。火災の拡大を招いた原因として、階段スペースに避難の妨げとなる物品が置かれていたこと、避難訓練が実施されていなかったこと、自動火災報知設備が正常に作動しなかったこと、そして防火戸が閉鎖されず煙が拡散したことなど、いくつもの防火管理上の問題が重なっていたことが明らかになっています。
こうした問題の多くは、防火管理の基本的なルールを守っていれば防げた可能性が高く、まさに「人災」と言える側面が強いものでした。火災による死者の多くは、炎によるやけどではなく煙による中毒死であったことからも、日常的な防火管理の徹底が命を守るうえでいかに重要かがわかります(なお、この火災をめぐっては、ビルの所有者や管理責任者らが業務上過失致死傷罪で起訴され、禁錮刑の有罪判決が確定しています)。
この火災を重く受け止めた総務省消防庁は、ただちに「小規模雑居ビルの防火安全対策」について消防審議会に諮問し、同年12月26日に答申が取りまとめられました。
この答申では、同様の小規模雑居ビルにおける安全確保のために必要な対策が多角的に示されており、後の消防法改正の礎となる内容が盛り込まれています。その背景には、都市部に数多く存在する老朽化したビルや、複数のテナントが入居する建物に共通する、防火上のリスクに対する強い危機感がありました。

答申の教訓を現場で実践―私たちの防火管理サポート体制
消防審議会が取りまとめた答申では、今後二度と同様の悲劇を繰り返さないために、特に重要とされる三つの対策が柱として掲げられました。
これらの対策は、火災の教訓をふまえて、制度・現場・地域といった多方面から防火体制を見直すものであり、実効性のある防火安全対策として後の消防法改正にも大きな影響を与えることとなりました。
こうした流れを受けて、私たち民間事業者にも、防火管理の担い手としての責任がより一層求められるようになっています。そこで以下では、答申で示された3つの対策の柱を整理するとともに、それに対して当社がどのような取り組みを行っているかをご紹介します。
1.避難経路と防火設備の強化管理
最も重要な対策の一つとして挙げられたのが、避難経路と防火設備の管理体制の強化です。
特に「二方向避難の確保」や「防火戸の確実な閉鎖」といった、人命を守るために欠かせない基本的な設備が、非常時に正常に機能する状態で維持されていることが求められました。
明星56ビル火災では、防火戸が閉まらなかったことにより煙が急速に建物内に広がり、多数の死者を生む最大の要因となりました。この教訓から、答申では防火戸の前に物品を置く行為を消防法上で明確に禁止すべきとし、違反が確認された場合には、単なる注意にとどまらず、使用の停止命令などの強力な是正措置を講じる必要があると強く指摘されています。
また、避難口や階段などの共用部に荷物を置くことは、日常的には些細なことに見えても、非常時には命取りになりかねません。そのため、日常の清掃や点検の際に、避難経路が確保されているか、物が置かれていないかをしっかり確認し、必要に応じて写真付きの記録を残すといった、確実な管理の実施が推奨されています。
2.点検報告制度の整備
二つ目の柱は、防火管理の実効性を担保するための点検制度の導入です。
従来は、建物所有者やテナントの自主的な管理に委ねられていた防火体制について、第三者である「防火対象物点検資格者」が定期的に点検を行い、その結果を消防署に報告する仕組みが提言されました。
これにより、形式的な管理ではなく、実態に即した点検と記録が行われ、問題があれば迅速に是正されるというサイクルが制度的に確立されることとなります。特に、一定以上の規模や構造、用途を持つ建物においては、管理者の「実行責任」を明確化し、自己点検だけでは見落とされがちなリスクを、専門的な知見を持つ第三者が補完することが期待されています。
点検の対象は、防火管理者の選任状況をはじめ、避難経路の確保状況、防火戸の閉鎖状態など多岐にわたります。この点検報告制度は、のちの消防法改正により制度化され、現在では一定の条件に該当する建物において、年1回の防火対象物点検報告が義務付けられています。
3.地域啓発と多機関連携による対策強化
三つ目の柱は、防火意識を社会全体に浸透させるための地域啓発活動と、それを支える体制整備です。
答申では、自治会や消防団、商工団体、自主防災組織など、地域に根ざしたさまざまな団体と連携し、防火安全に関する知識や重要性を広く普及させていくことの必要性が示されました。
その具体策としては、パンフレットの配布、出張講習の実施、地域の防火リーダーの育成、オンラインを活用した情報発信など、複数の手法を併用した啓発活動が挙げられています。こうした取り組みによって、消防機関だけでなく、地域の一人ひとりが「自分たちの命は自分たちで守る」という意識を持ち、日頃の防火管理がより実効性のあるものになることが期待されています。
4.当社における対応とサービスのご案内
当社では、これらの答申内容をふまえ、現場での対応をさらに強化しています。
【防火管理者外部委託サービス】では、毎月の巡回点検を通じて、避難経路や防火戸まわりの安全性を重点的に確認し、問題があれば即座に是正対応を行う体制を整えています。
たとえば、避難通路に荷物が置かれていないか、防火戸の閉鎖を妨げる物がないかといった確認項目については、点検時に写真記録を残し、必要に応じてお客様に改善依頼を行っています。こうした現場対応の考え方については、「避難経路と防火戸管理を怠るリスクとは」というコラムにも詳しくまとめていますので、ぜひ参考にしてください。
また、一定の条件を満たす建物やテナントに義務付けられている「防火対象物点検報告」にも対応可能な【防火対象物点検サービス】を提供しており、防火管理者外部委託サービスとセットでご契約いただくことで、割引が適用されます。本サービスでは、点検時期が近づいた際に当社からご案内を差し上げるため、毎年の発注手続きが不要となるなど、手間なく継続できる点も多くのお客様にご好評いただいております。
小規模雑居ビルに広がる違反の現実―立入検査が浮き彫りにした課題
この答申を受け、平成14年には消防法が改正され、同年10月25日から施行されました。
この法改正により、消防機関による立入検査の体制が強化され、違反に対しては従来の警告や命令に加え、罰則の適用も明確に規定されるようになりました。
なかでも注目されたのが、全国的に実施された「小規模雑居ビルの一斉立入検査」です。
この調査では、点検を受けた建物の実に9割以上で何らかの消防法違反が確認されるという、衝撃的な結果が明らかになりました。中には、避難通路が完全に塞がれていたり、そもそも必要な消防設備が設置されていないなど、極めて危険な状態のまま営業が続けられていた事例も存在しました。
このような実態を踏まえ、多くの違反が是正されてきた一方で、すべての建物で十分な管理がなされているわけではないという課題も浮き彫りになりました。防火管理体制の整備が行き届いている建物もある一方で、そうでない物件との間には依然として大きな格差があり、違反の再発リスクも懸念されています。
そのため消防機関では、建物のリスクレベルに応じて、優先的に立入検査を実施すべき対象を選定し、管理者の対応状況に応じた柔軟な指導を行う必要があるとされています。さらに、ビルの所有者や管理者だけでなく、実際にその空間を利用し営業を行うテナント側にも防火意識を持ってもらい、共用部分の安全管理をともに担うという意識づくりが、今後の大きな課題となっています。