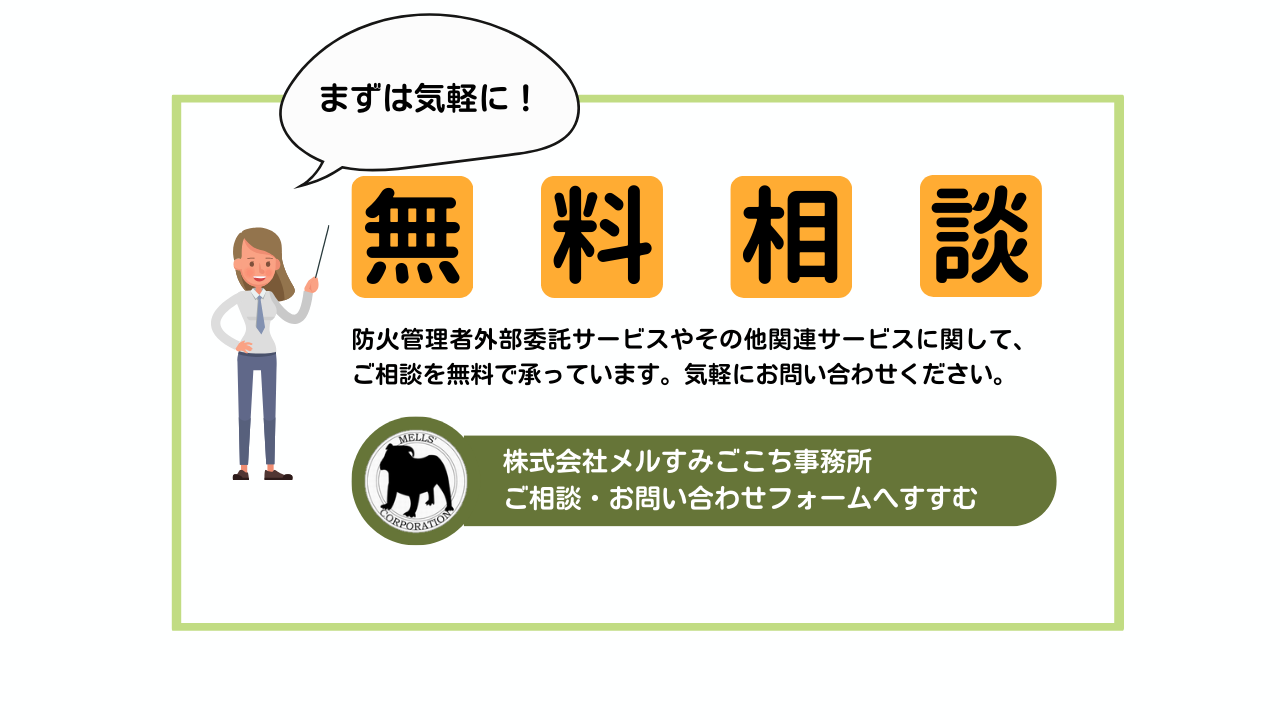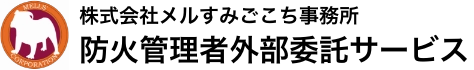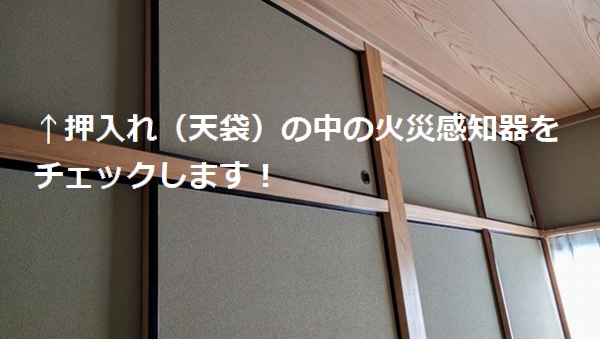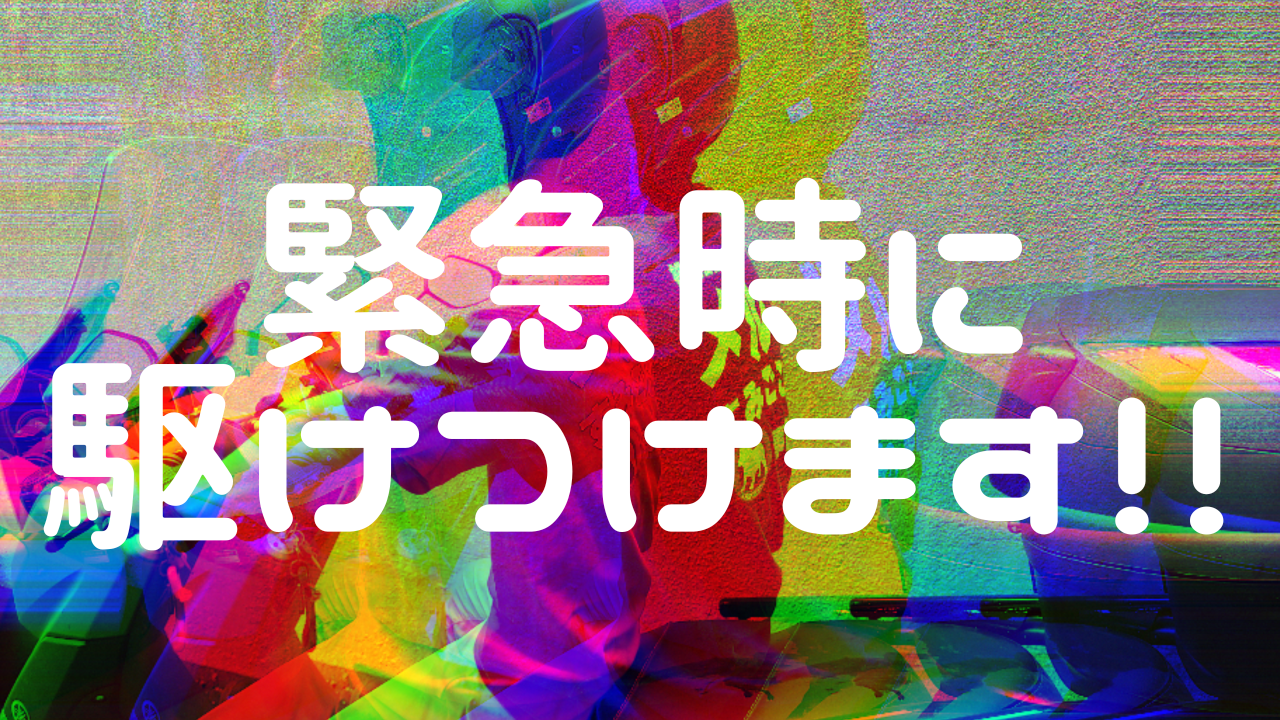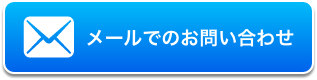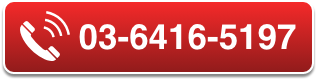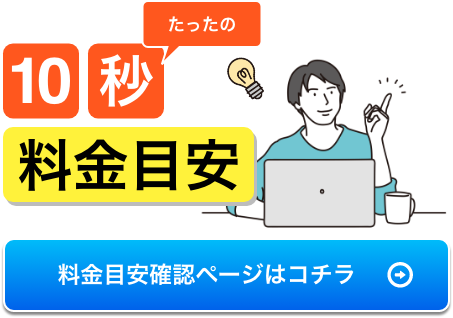消防署が「有事の駆けつけ」を重視する理由とは?防火管理者に求められる実効性と責任
当社の【防火管理者外部委託サービス】では、契約前に必ず管轄消防署へ外部委託が可能かどうかを確認しています。その際、消防署の担当者からよく投げかけられる質問の一つに「有事の際に防火管理者は現場に駆けつけられますか?」というものがあります。
一見シンプルな問いですが、その背後には「防火管理の実効性」や「名義貸し防止」といった重要な懸念が隠されていると考えられます。つまり、防火管理業務が実効性をもって機能しているかどうか、そして形骸化を防ぐために名義貸しを排除できているかという二つの視点です。
両者は一見似ていますが、前者は業務の「質や効果」に重点があり、後者は防火管理者が「実際に関与し責任を果たしているか」という担い手の実在性に重点がある点で異なります。
まず「防火管理の実効性」については、防火管理が消防法に基づく法的責務である以上、単に書類を整えるだけでなく、実際に機能しているかどうかが問われます。火災は発生からわずか数分で建物全体に延焼する可能性があるため、防火管理者が平常時からどのような備えを行っているかが、被害を最小限に抑えられるかどうかを大きく左右します。
次に「名義貸しの防止」については、防火管理者が名前だけを貸して実務に関わらない状態を指します。これは消防法違反であるだけでなく、重大事故を引き起こす要因にもなり得ます。消防署が「駆けつけ」という問いを投げかけるのは、防火管理者が本当に職務を遂行しているかどうかを見極めるための一つだと考えられます。
当社としても、こうした懸念を払拭し、「組織として防火管理体制を確立している」ことを明確に示すことが不可欠であると認識しています。
防火管理者の本来の責務とは?平常時に求められる業務と役割
消防法に定められた防火管理者の本来の責務は、火災現場に駆けつけることそのものというよりは、むしろ「火災を予防すること」や「万一の際に被害を最小化すること」にあります。
実際に、防火管理者に必要とされる平常時の主業務には、以下が含まれます。
- 「防火管理に係る消防計画」の作成・届出
- 消火、通報及び避難の訓練を実施
- 避難又は防火上必要な構造及び設備の維持管理
- 火気の使用又は取扱いに関する監督
《出典》東京消防庁 「管理権原者」とは・「防火管理者」とは
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/office_adv/jissen/p03.html
火災が発生し、消防隊が到着するまでのわずかな時間は、建物内にいる人々が自ら判断して避難や初期消火を行うしかありません。外部委託の場合、防火管理者が偶然その場に居合わせていれば避難誘導や初期消火にあたることもできますが、実際にはそうでないケースが大半です。
さらに、火災発生の報告を受けて駆けつけても、こうした対応に間に合うのは物理的に難しい場合が少なくありません。火災はいつ発生するか分からないため、このような状況は、24時間体制の防災センターを備えた大型施設などを除けば、ほとんどの防火管理者に共通する現実といえます。
そのため当社では、火災発生時に適切に避難できるようにすること、初期消火が可能な場合に消火器などの設備を正しく使えるようにすること、そして正確に消防機関へ通報できるようにすることを目的として、法律で定められた回数の消防訓練を毎年実施しています。加えて、訓練に参加できなかった方のために、注意点をわかりやすくまとめた「消防訓練の手引き」を全戸にポスティングし、周知徹底を図っています。
加えて、防火管理に特化した現地点検を定期的に行い、燃えやすいものを放置しない、避難経路をふさがないといった基本的な管理を徹底することも欠かせません。こうした日常の取り組みの積み重ねこそが、火災を未然に防ぎ、万一の際にも被害を最小限に抑えることにつながります。

防火管理者に「有事の駆けつけ」が求められる理由と3つの役割
防火管理者は火災発生時に必ずしも消火活動を行えるわけではなく、主な責務は「火災を予防すること」や「重大な火災事故を未然に防ぐこと」といった日常の防火管理にあります。初期消火が困難な段階になれば、実際の消火活動は消防隊の役割となります。
それにもかかわらず「駆けつけ」が問われるのは、「防火管理の実効性」や「名義貸し防止」といった防火管理体制の本質を確認する意味に加え、防火管理者に次のような役割が期待されているからだと考えられます。
1.鎮火後の調査協力
火災原因や責任の調査に協力し、平常時に点検や訓練を適切に行っていたことを証明する役割です。当社では、点検や訓練の結果を写真付き報告書として作成し、すべてをデータで一元管理しています。これにより、火災発生後の調査時にも客観的な証拠に基づいた説明が可能となり、防火管理が形骸化していないことを明確に示すことができます。
2.関係者への説明と橋渡し
管理権原者や管理会社に火災の状況を正しく伝え、消防とのやり取りを円滑にする役割です。当社では、専門知識を持った担当者が現場の状況を整理し、管理側と消防との間に立って適切な説明や調整を行います。これにより、現場で混乱が生じることを防ぎ、速やかに必要な対応につなげることができます。
3.誠実な姿勢の証明
緊急時に現場へ駆けつけるという姿勢そのものが、防火管理者としての信頼性につながります。当社では「駆けつけ」を単なる形だけの行為にせず、平常時からの点検・訓練・周知活動を土台に、いざという時には責任ある行動を取れる体制を整えています。こうした姿勢が、消防や管理者からの信頼の獲得につながっています。
防火管理を止めない組織体制|10年超・2,000件の実績と今後の取り組み
当社の強みは、防火管理を「個人」ではなく「組織」として運営している点にあります。この体制により、防火管理者が病気やけがなどで業務に支障が生じても、防火管理そのものが止まることはありません。組織として役割を補完し合うことで、現場での迅速な対応と、法令に基づいた確実な管理を常に維持しています。
さらに、原則として毎月行う巡回防火点検の結果は、すべて写真付き報告書としてデータ化され、オンラインで一元管理されています。これにより防火管理者は全物件の状況をリアルタイムで把握でき、緊急時にも即座に対応することが可能です。中央集約的な管理システムの導入により、組織としての実効性が一層高められています。
こうした取り組みを、事業開始以来10年以上にわたり愚直に継続してきました。その結果、ありがたいことに2,000件を超える物件を受託するまでに至り、現在に至るまで防火管理の不手際が原因で火災が発生し、被害が生じた事例は一件もありません。このように、私たちは個人に依存しない体制と日々の地道な取り組みを積み重ねてきました。これからも「安心して任せられる防火管理者」であり続けられるよう、努力を重ねてまいります。
なお、当社が提供する24時間緊急ダイヤルや、いざという時に社用バイクで現場へ駆けつける仕組みについては、別コラム「防火管理者として火災発生時は迅速対応します!」でも紹介しています。