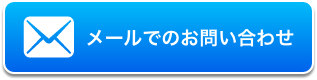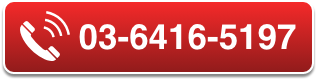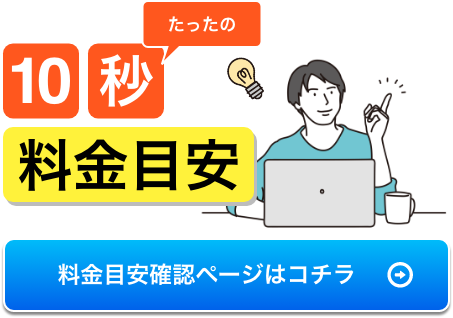インバウンド時代の民泊防火対策─総務省・東京消防庁の最新方針を解説
近年、訪日外国人観光客の増加に伴い、全国各地でインバウンド需要が高まりを見せています。それに呼応する形で、民泊施設の開業も急速に広がっており、当社にも民泊物件の防火管理に関するお問い合わせをいただく機会が増えてきました。
特区民泊や簡易宿所といった制度を活用した民泊施設は、観光振興や地域経済の活性化に寄与するだけでなく、空き家の有効活用という点でも一定の役割を果たしています。一方で、防火安全という観点から見ると、こうした施設の増加が新たな課題を浮き彫りにしているのも事実です。
民泊施設の運営形態にはさまざまなバリエーションがありますが、中でも特に多いのが、チェックイン・チェックアウトを非対面で行う無人運営型の物件です。ホテルのように常駐スタッフがいれば、火災発生時の避難誘導や初期対応も期待できますが、無人施設ではそうした即時対応が困難であり、火災時の被害拡大リスクが高まる恐れがあります。
加えて、利用者の多くが海外からの観光客であることも、防火対策上の大きな懸念材料となります。日本の建物構造や避難ルール、消防設備の配置・使い方について十分な理解を持っていない方も多く、言語や文化の壁が「もしものとき」の行動に影響を与える可能性があるのです。実際、火災時にどのように行動すればよいかを事前に把握していない宿泊者は少なくありません。
こうした背景を踏まえ、一部の民泊施設では、防火対策の一環としてさまざまな工夫がなされています。たとえば、消火器の設置場所を誰でも分かるようにピクトグラムで示したり、避難経路を多言語で掲示したりする取り組みが広がりつつあります。
それでもなお、多くの課題が残されているのが現状です。たとえば、「火災報知器が鳴っても意味が分からず行動できない」「非常口の場所が分からない」「消火器の使い方が分からない」「119番通報の方法が分からない」など、外国人宿泊者が直面する不安や障壁は依然として大きいままです。たとえ消防設備が適切に設置されていても、それが宿泊者にとって“使える”状態でなければ、安全が確保されているとは言えません。「設置してあること」よりも、「理解され、実際に使えること」がより重要です。
こうした現状を踏まえると、今後さらに多様化・無人化が進む民泊施設においては、施設の管理者が防火対策を“宿泊者の視点”で考え、設計・運用していく姿勢がこれまで以上に求められると言えるでしょう。
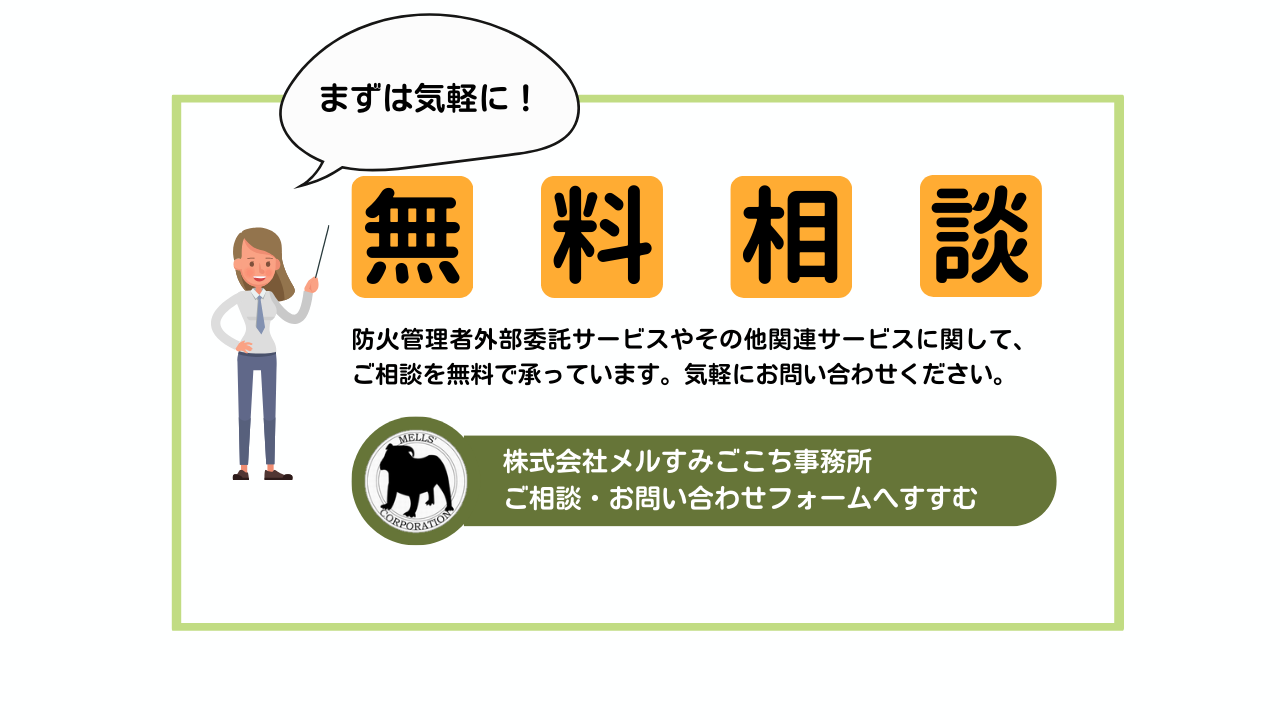
総務省消防庁発「消防予第135号」が示す民泊防火対策の方向性
こうした背景を受けて、総務省消防庁は令和7年3月28日付で「関係者不在の宿泊施設における防火安全対策ガイドライン(消防予第135号)」を発出し、東京消防庁および各指定都市の消防長宛に通知を行いました。
本ガイドラインは、無人運営型の民泊施設や、セルフチェックイン方式を導入している簡易宿所などを想定した内容となっており、管理者や従業員が常駐していない宿泊施設における防火安全体制の強化を強く求めています。
特に、本通知では、火災が発生した際に宿泊者自身が初動対応を行わなければならないという現実を踏まえ、平時からの防火対策情報の明確な周知が不可欠であることが明記されています。消防設備の使用方法や避難行動などを、事前に分かりやすく伝えておくことが、宿泊者の安全確保に直結するという考え方が示されています。
なかでも注目すべき点は、宿泊者に対して以下のような具体的な対策を講じることが求められていることです。すなわち、「火災予防や避難に関する情報提供を積極的に行うこと」「避難経路図や消火器の設置位置を、外国人旅行者にも直感的に理解できるように表示すること」「通報方法や避難の手順を、誰でも理解できる形で明示すること」などが挙げられています。これらはいずれも、宿泊者の立場に立ったアプローチであり、単に設備を整備するだけでなく、「伝わる防火対策」を実現することの重要性が強調されています。
なお、この通知は努力義務として位置づけられているものの、万が一火災が発生し、適切な対応が取れなかった場合には、施設の信用や経済的損失にとどまらず、人命にかかわる重大な結果を招くおそれがあります。そのため、事業者として本通知の内容を真摯に受け止め、主体的かつ具体的な対策を講じていくことが強く求められます。

東京消防庁ホームページで学ぶ、宿泊者への防火対策
無人で営業を行う民泊施設などに対する国の方針に呼応し、東京消防庁でも防火安全に関する啓発活動が進められています。東京都内で民泊施設を運営する事業者向けに、公式ホームページ上に「民泊事業者向け防火安全対策」ページを開設し、宿泊者への注意喚起に活用できる各種リーフレットを無償で提供しています。
リーフレットの内容には、コンロや電気ストーブの使用方法と取り扱い上の注意点、喫煙ルール、消火器の使用方法、火災発生時の通報手順などが網羅されており、民泊施設における火災予防と初期対応に役立つ実用的な情報が掲載されています。
これらのリーフレットは、日本語のほか、英語・中国語・韓国語などにも対応しており、外国人宿泊者への配慮もなされています。施設内の掲示物として設置するだけでなく、客室内に常設資料として備えることも想定されており、宿泊者の安全意識を高めるツールとして非常に有効です。
《出典》東京消防庁「新たに民泊を行おうと考えている皆様へ」
https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/lfe/office_adv/minpaku.html
当社では、こうした行政の方針を踏まえ、従業員が常駐していない民泊物件等を運営されている事業者との契約時に、東京消防庁のホームページをご確認いただくとともに、同ページ内で提供されている宿泊者向けリーフレットの設置をお願いしています。
特に、無人運営であり、かつ利用者の多くが外国人であるような施設では、火災の原因となり得る行動への注意喚起や、火災発生時における初期消火・通報といった初動対応を、宿泊者自身が行わなければならないケースが想定されます。そのため、平常時からの備えが極めて重要となります。
このような状況下においては、掲示物やリーフレットといった情報提供ツールが、非常時における適切な判断や迅速な行動につながり、結果として利用者の命を守るだけでなく、運営事業者自身を守ることにもつながるという点を、改めて認識しておくことが重要です。
地震大国である日本において、火災は「いつか起きるかもしれない」ものではなく、「いつ起きてもおかしくない」災害であるという意識を、私たちは常に持っておく必要があります。また、観光立国を掲げる中で、外国人宿泊者が安心して滞在できる環境を整備することは、受け入れ側の責務とも言えるでしょう。そのためには、設備面の整備だけでなく、情報提供や体制づくりといった“ソフト面”の充実も欠かせません。
施設の規模や営業形態にかかわらず、すべての宿泊事業者に防火意識の浸透と、具体的な取り組みが求められています。当社では引き続き、宿泊施設を運営される皆さまの防火管理体制の構築・強化に向けた支援を行ってまいります。
ご不明な点やご相談などがございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。
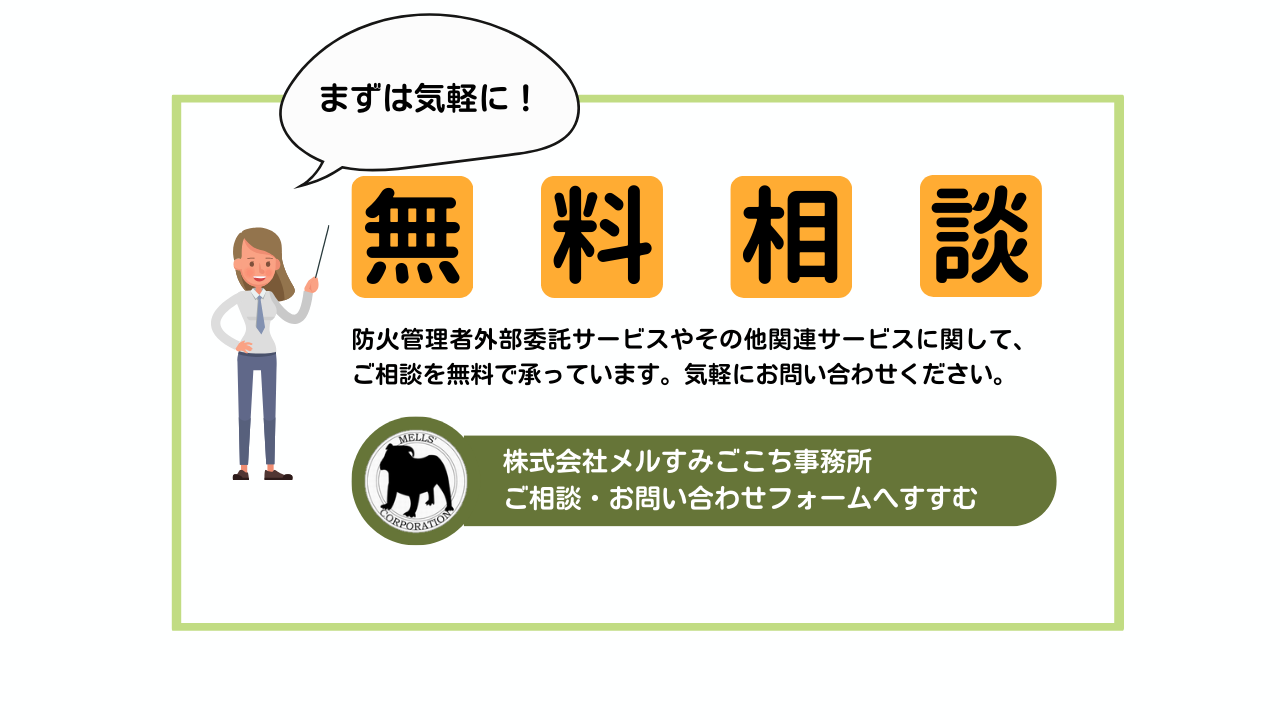
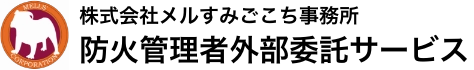

管轄:新宿区歌舞伎町.jpg)